閉店間際の石丸電気にハイエナのように群がるクラヲタの一員となってCDを買う。3割引だから…って言うのもあるんだけど、もう石丸でCDを買うこともなくなるんだなぁ、と言う、少なからぬ感傷的なものもある。最初にCDを買ったのは、石丸だし、ずっと通い続けていた。やっぱ寂寥感。
最初の頃買っていたのは、モーツァルト、そして、ハイドン。それから、ロマン派に流れて行って、マーラーやブラームスを聴くようになったのかな。ヴォーン=ウィリアムズのCDを片手に「面白そうだけど、どんな作曲家なんだろう?」とジャケットを眺めて悩んでいたこともあった。
そして、今、買っているCDは古楽が増えた。この閉店セールでも随分と古楽のCDを買っていくことになるだろう(セールは3月27日まで)。
そんな中から1枚。ちょっと前に紹介した、レ・ウィッチーズの演奏したプレイフォードの『英国の舞踏指南』。レ・ウィッチーズ、以前紹介したとおり「魔女たち」と言う意味で、鍵盤奏者を除いて全員女性である。と言っても、女性ってことばかりを売りにした団体ではない。奏者はそれぞれ、レザール・フロリサンなど欧州各地の有名どころの古楽団体に参加している実力派集団。以前紹介した『デンマークの王宮、フレゼリクスボー城の音楽~クリスチャン4世の時代より~』もそうだがユニークな企画がヲタク心をくすぐる楽団だ。
で、今回買ったCDなんだけど、タイトルの通り、イギリスの音楽である。対して、レ・ウィッチーズはフランスの楽団。これもちょっとした変化球だ。ロマン派以降であれば、例えば、ラヴェルをビーチャムがロイヤル・フィルを振って演奏しても不思議じゃないんだが、『英国の舞踏指南』…って(汗)。
さて、プレイフォードとは何者か。おいらもよく知らない(汗)。知っていることは、プレイフォードは作曲家ではないと言うこと。出版業者、なのかな。なんか、そんな立場で、イギリス各地の伝統音楽を収集して、出版していた。アイルランド民謡とか、ケルト系の音楽も随分と集めた。CDの解説によると(輸入盤ながら詳細な解説書が付いている)、この世ではじめてのケルト音楽の収集記録を作った、と言うことになる。
さっくりジャンル分けをしたがる人なら、「これは民族音楽」と簡単に定義付けるだろう。しかし、グレインジャーを簡単に「民族音楽」と仕分けられないのと同じようにこの音楽も単なる「民族音楽」ではないんである。かと言って、クラシックかと言うと、それもまた微妙。いや、トルバドゥールを中心とした中世音楽、更に、ルネサンス音楽も少し考えれば判るけど、世間が高尚と崇めたてているクラシック音楽とは少し異なる。もっと言ってしまえば、バロックや古典派だって…と、まぁ、話を進めていくととりとめがないのでやめておくが、さっくりジャンル分けができるはずがないのが、西洋音楽史である。まぁ、ひっくるめてヨーロッパの民族音楽と言ってしまえばいいんだが。
…と話がそれた。『英国の舞踏指南』なんだが、これ、舞踏と言うだけあって実にリズミカルで心地よい音楽だ。と言っても、のうてんきで明るい音楽ではない。何とも、深い哀愁が漂う。ケルト系音楽の魅力だろう。そんな音楽をレ・ウィッチーズが上質な演奏で響かせる。もともとは村の集会所や宴の席などガヤガヤとしたところで、演奏された音楽だろうが、この演奏はとてもおしゃれに感じさせてくれる。野蛮な感じは全くしない。それでいて、音楽の内包する活力は決して損なっていない。ジャケットも美しくって、お勧め。値段はすごく高い。2,800円。石丸セールのうちに…って、おいらが買っちゃったからないかも。
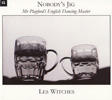
 [0回]
[0回]
PR
